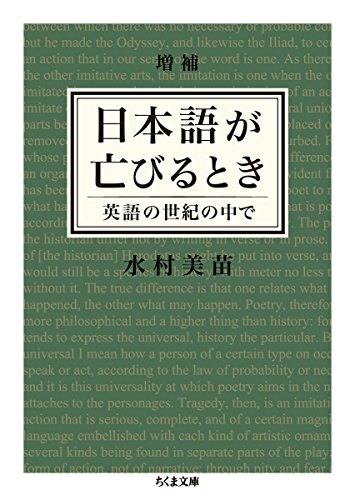評価:A
【評】
「人はなんとさまざまな言葉で書いているのか」
外国で非英語圏の人々と関わってきた著者がものした警世の書。
「パリでの話」は圧巻。たびたび挿入される『三四郎』の場面、
学問と<普遍語>の関係、<国語>の誕生など、厚いが面白い。
英語が<普遍語>になるとは、どういうことか。
それは、英語圏をのぞいたすべての言語圏において、<母語>と英語という、二つの言葉を必要とする機会が増える、すなわち、<母語>と英語という二つの言葉を使う人が増えていくことにほかならない。
世界を解釈するにあたって、 英語という言語でもって理解できる<真実>のみが、唯一の<真実>となってしまっているということを。
英語の世紀に入ったとは何を意味するのか。
それは、<国語>というものが出現する以前、地球のあちこちを覆っていた、<普遍語/現地語>という言葉の二重構造が、ふたたび蘇ってきたのを意味する。
<自分たちの言葉>で学問ができるという思いこみは、実は、長い人類の歴史を振り返れば、花火のようにはかない思い込みでしかなかったという事実である。<国語>で学問をしてあたりまえだったのは、地球のほんの限られた地域で、ほんのわずかなあいだのことでしかなかった。その時代は、長い人類の歴史の中では、規範的であるよりも、例外的な時代であった。
悪循環がほんとうにはじまるのは、<叡智を求める人々>が、<国語>で書かなくなるときではなく、<国語>をよまなくなるときからである。<叡智を求める人々>ほど、<普遍語>に惹かれてゆくとすれば、たとえ<普遍語>を書けない人でも、<叡智を求める人々>ほど<普遍語>を読もうとするようになる。
(中略)
そして、そのうちに<自分たちの言葉>からは、今、何を考えるべきかなどを真剣に知ろうなどとは思わなくなっていく。
処方箋はこれだ。
日本の学校教育の中の必修科目としての英語は、「ここまで」という線をはっきり打ち立てる。
(中略)
日本人は何よりもまず日本語ができるようになるべきであるという前提を、はっきりと打ち立てるということである。
日本の国語教育はまずは日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである。
一つには、それが「出版語」が確立されたときの文章だからである。(中略)
二つには、それが漱石がいう「曲折」から生まれた文学だからである。
「古典とのつながりを最小限度に保つ」――みながそのつながりを保っていれば保っているほど、日本語は生きている。