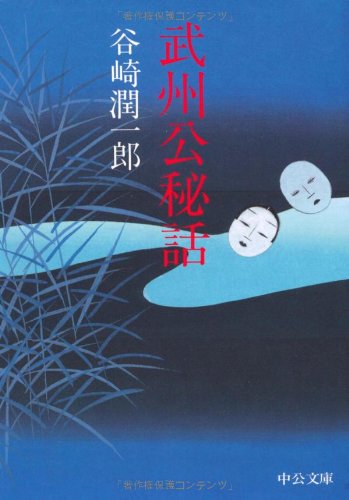もうその仕事に馴れ切って、無表情に、事務的に働いているその女たちの容貌は、石のように冷たく冴えていて、殆ど何等の感覚もないように見えながら、死人の首の無感覚さとは無感覚の具合が違う。一方は醜悪で、一方は崇高である。そしてその女たちは、死者に対する尊敬の意を失わないように、どんな時でも決して荒々しい扱いをしない。出来るだけ鄭重に、慎ましやかに、しとやかな作法をもって動いているのである。
此の室内を領しているものは夥しい首、「死」の累積なのである。そう云う中にあってその娘の持つ若さと水々しさは一層引き立って見えたであろう。たとえば彼女の紅味のさした豊かな頬は、青白い首の血色と対照されるときに、その本来の紅さよりも以上に生き生きとしたものに思えたであろう。(中略)そして法師丸は、今夜も亦彼女の眼元と口元に浮かぶ不思議な微笑を見たのであった。
法師丸は、その美女の前に置かれてある首の境涯が羨ましかった。彼は首に嫉妬を感じた。ここで重要なのは、その嫉妬の性質、羨ましいという意味は、この女に髪を結って貰ったり、月代を剃って貰ったり、あの残酷な微笑を含んだ眼でじっと視つめて貰ったりする、そのことだけが羨ましいのではなく、殺されて、首になって、醜い、苦しげな表情を浮かべて、そうして彼女の手に扱われたいのであった。(中略)死んでしまえば知覚を失うことぐらいは、彼にも分っていた筈である。だから、首になってこの女の前に置かれることが幸福だと云う空想は、それ自身に矛盾があり、ただその空想だけが楽しいのである。少年は、自分が首になりつつも知覚を失わないでいるような妄想を描き、それに惑溺したのである。彼は女の前へ順々に運ばれる首を、一つ一つ自分の首であるかのように考えてみた。そうして彼女が櫛の峰を以て首の頂辺を打ち叩くとき、自分が叩かれているように考える、―――すると、彼の快感は絶頂に達して、脳が痺れ、体中が顫えるのであった。